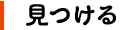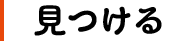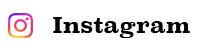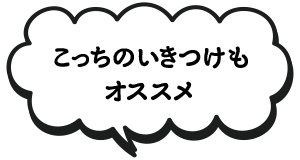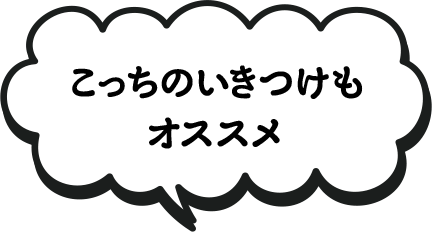秋葉原の喧騒から避けるように10分ほど歩くと、昔ながらの情緒あふれる建物が残る神田淡路町にたどり着く。あんこう料理の『いせ源』や、日本蕎麦の『まつや』といった老舗の看板が出迎えるこの一角に店を構えるのが松栄亭。

夜の帳が降りると共に店頭に点る優しい灯りに誘われるままに暖簾をくぐると、シンプルなテーブル席が待つ洋食店。格式張ることなく普段遣いができるこの雰囲気がありがたい。

その数時間前のこと。
「はじめまして」の一言と共に手渡された名刺。そこには昭和時代から使われるお店のシンボルマークと共に、『松栄亭四代目』と書かれていた。
この老舗の暖簾を守る堀口毅さんの手はがっしりと逞しく、頼りがいのあるという言葉がしっくりきた。東京の真ん中で百年以上に渡って営みをつづける洋食店、その歩みは明治中期に生まれた一つの出会いから始まった。
◯夏目漱石との出会いと、人生を決めた一つの料理

明治26年、時の明治政府によってドイツから招聘されたラファエル・フォン・ケーベル博士。東京帝国大学(現在の東京大学)の教授として教壇に立ち、哲学を専門に数々の知識を教えた。その専属シェフとなったのが、後に松榮亭の創業した堀口岩吉さん。
「当時、色々なルートで専属シェフを探していたようなんです」と、麹町の西洋料理店『宝亭』の料理人として腕を奮っていた岩吉さんに、白羽の矢が立ったという。
ある日、ケーベル博士が家に招いたのは、教え子・夏目漱石と幸田露伴の妹・幸田延子。家に招いた際に漱石は「何か変わったものが食べたい」と依頼した。そこで岩吉さんは、冷蔵庫の中にあった肉と卵を使い一つの料理を仕上げた。
アドリブで生まれたその一皿が、漱石をはじめその場にいた人に大好評を博したのは想像に容易く、岩吉さんの人生を大きく変えたものとなった。

後に『洋風かきあげ』と名付けられた料理と共に、岩吉さんが松栄亭を創業したのは1906年のこと。
その由来は正式な記録としては残ってないそうだが、「末広がりな感じがある松と『栄える』の言葉を組み合わせたんじゃないかな」という屋号は、この町に自然と馴染んでいった。
その後、岩吉さんから暖簾を受け継いだのは「第2次世界大戦の時に、現地の兵士に対して食事づくりをしていた」という信夫さん。実は急遽の流れだったそうだが、調理経験もあって数々の料理がしっかり受け継がれたという。
そして、三代目として厨房に入ったのは、「天皇の料理番」として知られる秋山徳蔵の下、宮内庁で働いていた経験を持つ博さん。

「今の場所の隣にあったんだけど、左隣にちょっとだけ見える同和病院の建物の屋上が、『探偵物語』で松田優作さんの事務所という設定だったんだよ。だからこのあたりでしょっちゅうロケしてたし、ウチで食事のシーンを撮影してた」そう。
「信夫には子供が5人いて、その中で『お前が継げ』と指名された」こともあって、上野精養軒で15年ほど洋食の修行に励んだ博さん。2つの場所で培った技を駆使してメニューとして始めたのがハヤシライス。今も色々な料理に欠かせないドミグラスソースの系譜は、更に広がりを見せることとなった。
◯調理法も姿も味も唯一無二!これが看板料理・洋風かきあげ

「自分は二人兄弟の次男、兄が『オレは継がない』と拒んだことで自分が継いだ」という毅さんもまた、父と同じく上野精養軒での修行を経て今に至る。
こうして四代に渡って受け継がれた暖簾の象徴は、やはり洋風かきあげ。その作り方を見せてもらうことにした。

松榮亭の味を決めるのはラードだと、毅さんは言う。
「一般的には豚の背脂だけど、ウチは昔から腹脂を使うことにこだわっている」というラードは、揚げたり焼いたりの調理過程すべてに使われている。
古くから馴染みだという精肉店から仕入れる極上ラードの揚げ油に、洋風かき揚げの生地が注がれる。
天ぷら粉で作られる普通のかきあげは、衣がサッと鍋の中に広がって軽やかな音と共に揚げられるが、こちらはポタポタと重厚感のある生地が少しずつ固まり、鍋から聞こえる音も穏やかだ。

フチを使い形を整えながら10分以上かけてじっくりと揚げていく。これだけの厚みを持つ生地ゆえ、揚げ時間が長くなるのは当たり前だが、生地の表面が黒く焦げたりといったことは一切ない。

「これだけ時間がかかる料理だから、焦げ付かないように揚げ油の温度が高くなったら、一旦別の容器に移して適温に調整してじっくりと揚げている」というのがその理由。
だからこそ、油の中でゆったりと泳がせることで生地にストレスが及ぶことなく、艷やかな色で仕上げられる。

想像を遥かに上回るサイズのかきあげが、目の前に運ばれてきた。心の底から思わず感嘆の声があがる。

ナイフでカットすれば中には玉ねぎと角切りの豚肉。ふんわりと立ち上る湯気からラードの甘い香りが微かに届く。生地の食感と玉ねぎのシャクシャクとしたアクセント、そして豚肉の弾力。シンプル具材が、不思議なほど奥深い味を作る。
唯一無二の生地の食感が洋風かきあげの醍醐味。薄く香ばしさを持つ表面と弾力に富んだ生地の二層仕立ては、見た目の迫力はもちろん、それ以上に一口一口が楽しい。
何より最後の一口まで重たさを感じさせない。これこそが上質なラードが生み出すおいしさなんだろう。

ほんのりした塩味が舌にやさしく、その加減が心地良い一品。そこに「親父の代からこれにした」というプリンスのウスターソースを注いで食べると、爽やかな酸味が生地のコクを際立てキリッと引き締める。
粉もの料理はソースの味に引っ張られることも多いが、これはブレない。むしろソースをかけることで、その地力を再確認することになる。最後の一口まで食べ飽きない奥深さをシンプルな姿に包み込んだ一皿は、まさに四代受け継がれてきた看板の味だ。
◯じっくり仕上げたデミグラスソースをたっぷり纏わせたビーフハンバーグ

お店の一角には初代から受け継がれてきた名作とともに、厨房を守ってきた職人が生み出した料理が記された木札が並ぶ。
「上の段の料理は、ほとんどがひいお爺ちゃんが作ったもの」という一方、「自分が始めたもの」と毅さんが挙げてくれたのが、デミグラスビーフハンバーグだ。

熱々のフライパンでこんがりと焼かれるハンバーグ。もちろん、これもラードが欠かせない。

その上に注がれるデミグラスソース。香味野菜に牛骨・鶏ガラを一週間ほどじっくりと煮込み、何度も濾した濃厚なスープと、しっかり煎ったルーを合わせて作られる。

噛みごたえに富んだ食感のハンバーグ。その強さに応じるように肉汁がじんわりと自然に染み出してくる。舌に伝わってくる牛肉の香りと風味は澄んでいる。これを彩るデミグラソースの豊潤な味は懐深くスッキリしてる。
「三週間に一度、大鍋いっぱいに作る」という味には、素材の旨味ともうひとつの店の看板たる矜持が詰まっていた。
◯門外不出の味を守る、その一つの答え

「本当は修行先でフレンチも学んだから、もっと色々な料理を作れるんだけど、それはひいお爺ちゃんに申し訳ない。新しい取組をするのは、昔から培われてきたものを守ってこそだね」
という毅さん、実はお店の料理づくり全てを一人で担っている。
「特にランチタイムは一人で切り盛りするのは大変だけど、大事なのは慣れだね」と、肉体的な負担は大きい。それでも自分のスタンスを崩さない背景には、初代への敬意がある。
「基本的に自分は、ひいお爺ちゃんの味を守るために今も店をやっているんですよ。例えば、ドミグラスソースとは別に、昔からポークソテーとかに使っているソースがあるんだけど、それは『門外不出』。二代目の時代に足繁く通ってくれた作家さんが体調を崩してしまって、『もうすぐ店に来れなくなるかもしれない。だからポークソテーのソースの味の秘密を教えてほしいんだ』と言われたけど、お爺ちゃんは首を縦に振ることはなかった」

百年以上に渡って一子相伝で受け継がれてきた味を守るため、毅さんは今日も一人で厨房に立つ。ランチタイムの営業を終えた休憩時間にも、一つひとつ丁寧にカトラリーをナプキンに包む。
その背中は、暖簾を守るというのはこういうことなんだと、静かに教えてくれているようだった。
【お店情報】
創業年:1907年(明治40年・取材により確認)
住所:〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-8
電話番号:03-3251-5511
営業時間:11:00~14:00/17:00~19:30
定休日:日曜日・祝日
おすすめメニュー:
洋風かきあげ(950円)/デミグラスビーフハンバーグ(1,500円)/ポークソテー(1,000円)/ポテトサラダ(600円)
※店舗情報は2019年11月16日時点、料金には消費税が含まれています。